「国語のテスト勉強って、いつから勉強すればいいんだろう?」
数学や英語はワークがあるけれど、国語は「何をすればいいのか」が見えづらい。だからつい、テスト直前に教科書を読むだけで終わってしまう中学生が多いのです。
でも、国語の定期テストで点を取るには、前もって準備する時間が絶対に必要です。
この記事では、中学生が国語の定期テストで失敗しないための「勉強を始めるタイミング」と「勉強の流れ」をお伝えします。
国語だけ後回しになっていませんか?
多くの中学生が、テスト期間になるとこう言います。
「国語は最後にやる。勉強しても意味ないから。」
でも、実はこの考え方こそが点数が伸びない最大の原因です。国語のテストは「記憶」ではなく「理解」を問われる科目。本文を何度も読み、設問に準備する時間が必要なんです。たとえば光村書店の教科書なら、「あの人の声」「握手」「走れメロス」など、深い読み取りが求められる題材が多いですよね。
1回読んだだけでは、登場人物の心情や場面の変化をつかみきれません。だからこそ、前もって読み込む期間が欠かせません。
テスト1週間前からでは遅いですよ。
理想的なテスト勉強スタートは、テスト2週間前。
これは、教科書本文→ワーク→見直しの3ステップを「余裕をもって回せる」タイミングです。
1週目は教科書本文の読み込み。
・教科書本文の理解
・漢字と語彙の暗記
この2点をしっかりしておかないと、2週目の対策が効果を十分に発揮できません。
2週目は学校ワークとノートの暗記。
・学校ワークを演習
・授業ノートをチェック
ワークとノートからテストにそのまま出ることがあります。しっかり暗記しましょう。記号の問題は、記号の中身もしっかり覚えること。
この流れを踏むと、文章の内容が自然と頭に残り、設問を読んだときに「この場面だ」と思い出せるようになります。つまり国語の定期テストは、国語のセンスではなく「準備力」で勝てるのです。
勉強の流れはこの3ステップでOK
① 教科書本文を音読+要約する
声に出して読むと、登場人物の気持ちや場面の雰囲気がつかみやすくなります。「この段落の要点を一言で言うと?」と問いかけながら読むのがおすすめです。「この部分を読むときはどんな調子で読めばいいですか?」という設問も入試に出るので、音読を軽んじてはいけません。
② 学校ワークで出題パターンをつかむ
ワークは「出題傾向の宝庫」。問題文の聞き方(たとえば「どのような気持ちですか」「理由を書きなさい」)に対してどのように答えるか。解答の作成パターンを覚えるのです。ワークは「1回やって終わり」ではなく、「3回やって答え方を覚える」のです。
③ 問題文の「根拠」をノートにメモする
記述問題でつまずく子の多くは、「本文のどこから答えを導くのか」を見つける練習をしていません。本文に線を引き、根拠をノートに書く。問題集の解説を自分で作るのです。この「根拠メモ練習」が、国語力を一気に引き上げます。
授業こそ、最高のテスト対策!
忘れてはいけないのが、「学校の授業を大切にすること」です。
授業中、先生が何気なく言った一言。「ここ、テストに出るかもね」や、黒板にさっと書いた言葉。実はそれがそのままテストに出題されることがよくあります。
国語の先生は、本文の読み取り方や設問の意図を授業でたくさん話しています。ですから、授業中は「黒板に書かれたこと」だけでなく、先生の言葉も大事なヒントとしてノートにメモしましょう。
ノートを見返したときに、「先生がこの場面で強調していたな」と思い出せる生徒は、テストでも強いです。
授業を丁寧に受けることは、何よりの定期テスト対策です。
最後に――11月中旬ごろに予想問題を公開します!
「じゃあ、実際にどんな問題が出るの?」という方のために、光村書店の教科書を使った定期テスト予想問題を現在準備中です。光村以外の学校の方は、ごめんなさい!
11月中旬ごろに公開予定ですので、ブックマークしてお待ちください。国語が苦手なお子さんでも、定期テストで高得点を取るきっかけをお届けします。
テスト勉強は、早く始めた人が必ず伸びます。
「国語はセンスじゃない、準備で勝てる」――それを、このブログを通して伝えていきたいと思います。

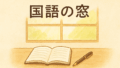

コメント